はじめに
最近コロナが流行してきたことで体温を測定する頻度が増えたと思います。そのとき、平熱が35度台という人がたくさんいます。これは体温がただ低いというだけではなく、身体に様々な悪影響を及ぼす可能性があることをご存じでしょうか。
そして体温が低い人は
やる気が出ない
運動不足
食欲がわかない
ストレスを感じることが多い
よく手先や足先が冷たい
といった状態になりやすくなります。このような状態になると身体の機能はますます低下し、日常生活にさまざまな影響を及ぼします。そして、この低体温の最も怖いのが『癌』のリスクが高まるということです。

私の個人的な見解ですが、最近テレビで癌の告知をされる芸能人の方がほんとに多い気がします。私が子供のころはテレビでこんなに頻繁にこのような癌のニュースは見なかった気がします。特に最近多くなってきたのは内臓の中でも「大腸癌」の割合が増えております。
そこで今回は癌になりやすい人の特徴とそれを予防するための方法についてお伝えしたいと思います。
癌が発生しやすい体温
まず癌には発生しやすい体温があります。そもそも癌細胞というものは健常な方でも毎日発生しています。しかし、免疫機能が働くことで癌細胞の増殖を抑えていることで癌にならずにいられるのです。
そこで免疫機能が働きやすい体温は一般的に36.5度以上といわれております。しかし、現代では平熱が35度台という方がとても増えました。この35度台という体温こそ癌の発生率が増加する体温なのです。

体温と免疫力の関係
生物には病気やウイルスから身を守るために免疫機能というものが備わっています。この免疫機能によって私たちは体内にウイルスなどが侵入しても身体の状態を維持することができます。
もしウイルスによって身体が侵された際はこの免疫機能によってウイルスを攻撃するように身体は反応します。その際に身体は熱を発生し身体の温度を上げようとします。
しかし、低体温の人は体温を十分に上げることができないため、免疫機能がうまく発揮しずらい状態となります。

そのため、低体温の人は体温が高い人と比べて病気になりやすい状態というわけです。
体温を高める方法の一つに『入浴』があります。入浴時にその日の身体の状態に合わせて温度を調整することでより身体を良い状態へと高めることができます。身体の状態に合わせた入浴方法についてはこちらの記事をご覧ください。
低体温の原因
昔と現代の人でどうして体温に差ができてしまったのか皆さんご存じでしょうか。その原因としては今と昔の生活様式の違いによる影響が大きいと思われます。 そしてその生活様式の違いによって大きく変化したのが、食事と運動になります。
運動不足による影響
体温を発生させるのに欠かせないのが筋肉になります。昔は歩いたり自転車で行くようなところでも現代ではその短い距離でも車を使うことが増えました。
また、最近ではコロナの影響で外出する機会がさらに減り、仕事もテレワークといった様式で働く人が増えてきました。そのため、一日の移動量が極端に減ってしまい昔の人と比較して現代の人の方が筋力が衰えている傾向があります。

一日の移動量としておすすめなのが男性は8000歩、女性は6000歩といわれております。
今ではスマホに歩数が計測できる機能が備わっていますので、一度一日の歩数を確認してみましょう。
誰でも簡単にできる運動にウォーキングがあります。しかし、このウォーキングもただがむしゃらにやるとかえって足に負担をかけてしまう原因になります。そんなときに大切になるのが『歩き方と靴選び』になります。歩き方のコツと自分の足に合った靴を知りたいという方はぜひこちらの記事もご覧ください。
食事内容による影響
食事内容による違いによって何が変わるのか、その一つとして咀嚼の回数になります。咀嚼機能とは食べ物を噛んで細かく分解するための大切な作業になります。

この噛むという作業は交感神経刺激し身体の熱を生成するとても重要な動きになります。しかし、現代では比較的柔らかいものが増え、あまり咀嚼をせずに飲み込むようにして食事をとる人が増えました。そのため、食事によって体内の熱を生成することが苦手な人が増えている傾向にあります。
これらの要素によって結果的に現代の人は昔の人と比べて体温を作り出す機能が低下してしまったというわけです。
食事と内臓機能の関係について
体温を高めるのに重要なのは筋肉だけではなく、もう一つに内臓があります。この内臓機能を高めることで代謝の効率を上げ、体温を高めることができます。
今回は内臓の中でも特に栄養素を取り込むための重要な臓器である『腸』についてお伝えしたいと思います。
昔と今の食事の違いについて
約50年前の食事と今現在の食事ではいったい何がちがうのでしょうか。大きく変わったこととして食物繊維の摂取量低下があります。昔の映画やドラマを思い出してみてください。テーブルの上に並べられた食事はご飯に味噌汁、魚、おひたしや野菜の煮物といったメニューが思い浮かぶのではないでしょうか。

そのイメージ通り約50年前の食事は「一汁三菜」の食事が主流でした。メインのおかずとしては肉はめったにとらず、主に魚が主体でその他に野菜や海藻、豆、イモ類などが食卓に並べられることがほとんどでした。
しかし、現代は朝食はパンとコーヒー、昼食は麺類や丼物、夕食は肉が主体というような食生活がごく一般的になってきていると思います。
なぜ現代の食事が腸を冷やすのか
食物繊維の摂取量が減ることでまず腸に影響することとして「排便力の低下」があります。
1950年ごろの日本人は1日に25g前後の食物繊維をとっていましたが時代とともに減り続け最新の調査では現代の日本人の食物繊維の摂取量は14.4gまで減ってきております。
(参照:平成29年「国民健康・栄養調査」)
食物繊維は人間の腸ではほとんど消化・吸収されずに大腸に運ばれ、そこで水分の吸収を行います。するとほどよい柔らかさの便が生成され大腸の腸壁を刺激し排便を促します。また食物繊維は善玉菌のエサになるため、腸内環境を整えるのにもとても大切になります。
このことから現代の食事では食物繊維の摂取が減ることで大腸への刺激が少なくなることが予想できると思います。すると腸の動きは悪くなりいわゆる停滞腸の状態となります。
この記事以外にも『腸』に関する記事をまとめていますので、興味のある方はぜひこちらの記事もご覧ください。
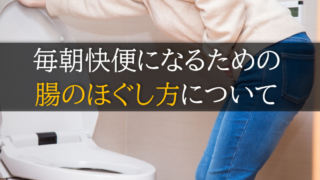
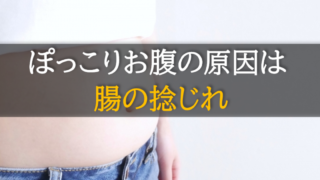
体温を上げるポイント
体温を上げるコツとして温かいものを飲むことをお勧めします。そして必ず朝食を摂るということが大切です。朝食を摂ることの最大の目的は腸の大蠕動を起こすことにあります。この大蠕動は腸や胃がからっぽの状態で食べ物を摂る朝食時に最も起こりやすく、この大蠕動が起きることで腸の動きが活発になり腸の冷えを軽減させてくれます。
そのため、ダイエットや時間がなくて朝食を抜いている方は腸の動きが悪い可能性があります。明日からは必ず朝食を摂るように心がけましょう。
体温を上げるおすすめ商品
腸を温める飲み物としておすすめはココアになります。ココアは生姜よりも長い時間保温効果がありゴボウよりも多く食物繊維を含んでいるのです。腸の動きを良くしたい、腸を温めたいと感じている方はぜひココアを飲んでみましょう。

最後に
皆さんいつも何気なく食べている食事について今回は真剣に考えてもらえたでしょうか。現代は飽食の時代です。食事に困ることなくお金を払うことで好きなものを食べることができます。それは一見良いことのように聞こえますが、なんでも食べることのできる時代というのはとても怖いです。その人の身体を作るのは何を食べたかによって大きく変わります。しっかりと個人個人が食の知識、そして内臓の知識を持つことで普段の生活を改めましょう。それが今後の病気の予防につながると思います。今回はその中でも一番怖い癌について少しお伝えしました。しっかりと体温を上げ、癌になりにくい身体を作りましょう。
本日もご覧いただきありがとうございました。

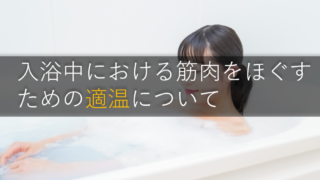
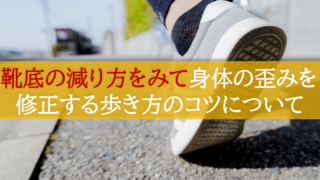
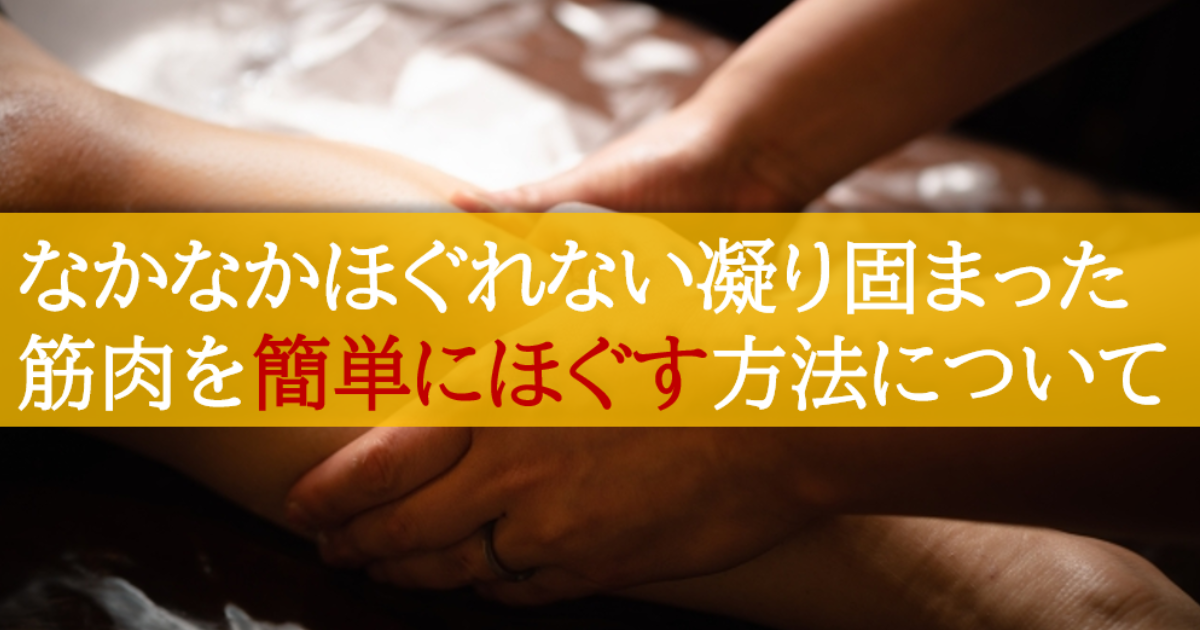
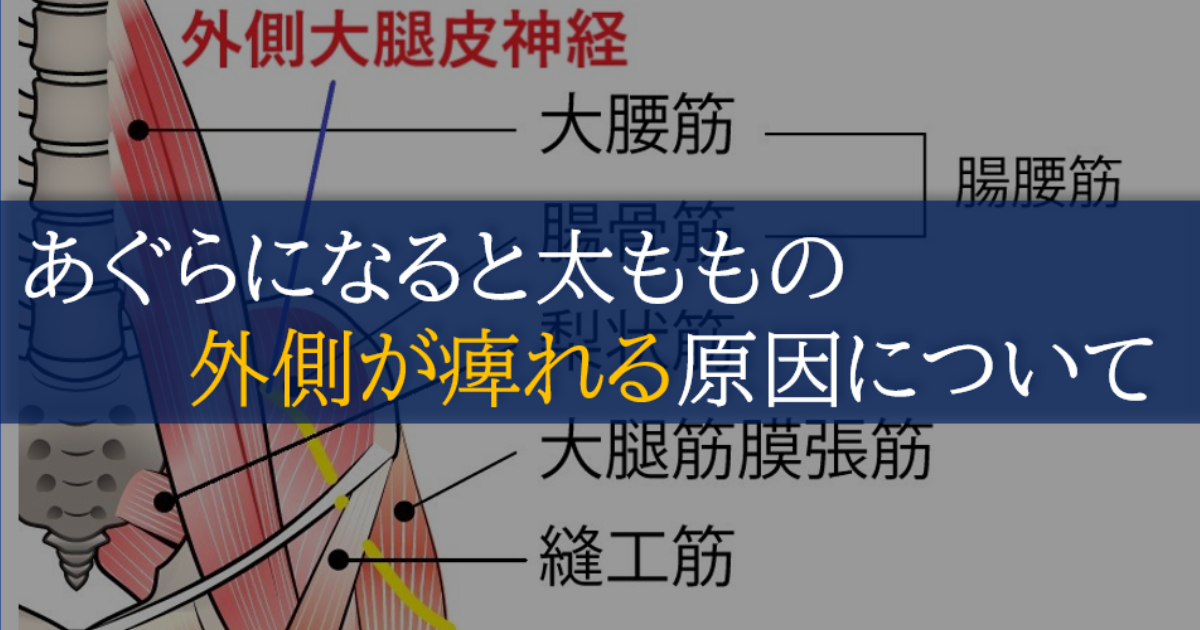
コメント